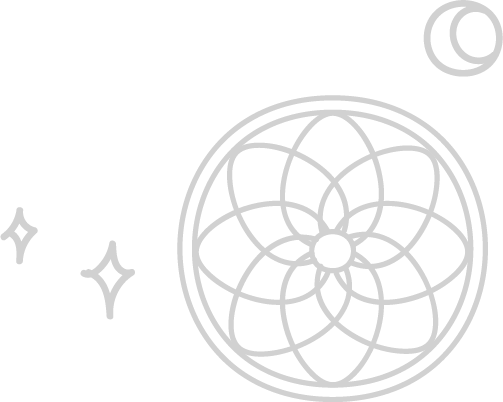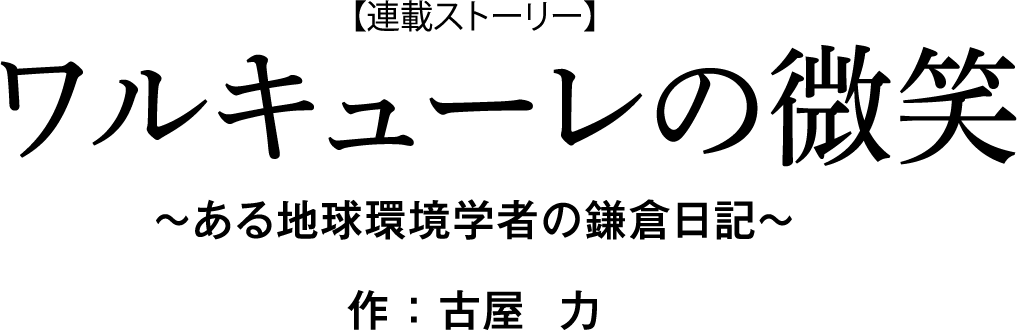
2022.8.30 掲載
もうすぐ退院も真近の病室で、山岡に、COP26(第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議)に現地で参加していた友人から一報が届いた。
交渉が難航し、会期を1日延長して、ようやく、11月13日に、成果文書「グラスゴー気候合意(Glasgow Climate Pact)」を採択して閉幕したとの報であった。その後の内外ニューズでも、COP26閉幕について、様々なコメントを付して報道がなされていた。
今回のCOP26では、途上国も積極姿勢を示した。排出量世界3位のインドは、2070年までに温室効果ガスの排出をゼロにすると宣言し、30年には再生可能エネルギーの比率を50%にする目標を示した。また、タイやベトナムは、2050年ゼロを表明。先進国と同水準の目標をかかげた。
今回の宣言で、産業革命前からの気温上昇は1.5度以内に抑える目標を、明記した点は、よかった。従来の「パリ協定」のコンセンサスでは、2.0度以内に抑えることを目指す一方で、あくまで、1.5度以内は、努力目標的な位置にあったが、それを一歩踏み込んで、1.5度以内に抑える目標を明記したのである。
2015年に誕生した「パリ協定」は、地球気温上昇を産業革命前から、できれば1.5度以内に抑えることをめざす、画期的な全員参加型の地球温暖化対策の国際枠組みであるが、方や、現状の各国の排出削減目標では達成できない厳しい現実がある。こうした事情を念頭に、今回の「グラスゴー気候合意」では、来年2022年末までに2030年の各国目標を見直すことも明記した。
しかし、一方で、とても残念だったのは、最大の焦点だった石炭火力発電利用廃止についての言及が、後退してしまったことであった。「グラスゴー気候合意」では、当初の文書案から表現を弱め、「段階的な廃止(phase-out)」から「段階的な削減(phase-down)」に変更したことは、明らかな後退である。46ヵ国が石炭火力発電の廃止、新規建設停止に同意したが、日本は同意しなかった。この後退に、日本も加担したことが、とても、残念でならなかった。日本人として、恥ずかしい気分になった。
今回のCOP26は、「3C+T」が鍵だと言われてきた。3Cとは石炭(Coal)、自動車(Car)、資金(Cash)の3点。 Tとは森林(Tree)である。その肝心の石炭への危機感が、日本も、すっぽり欠落したのである。よりによって、こうした「3C+T」を軸とした脱炭素社会に向けた世界の潮流を読まないかのように、COP26会場での日本の首相演説は、この期に及んで、石炭火力発電の利用について旧態依然として固執した内容であったことに、多くの会場参加者は、耳を疑い、大きな失望をした。
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)によると、1.5度に抑えるには、30年時点で10年比45%減が必要だが、気候変動枠組み条約事務局によると、現状の各国の取り組みを前提にシミュレーションすると、13.7%も増える予想であり、皮肉にも、「パリ協定」の目標達成から、どんどん、遠ざかってきてしまっている。これでは、人類は、気温上昇を1.5度未満に抑えることに失敗すると、焦燥感を、山岡は感じた。
昨日の「グラスゴー気候合意」を受け、日本の今後の帰趨に、世界の注目が集まっている。石炭火力発電所の段階的な削減の方向性が明記され、国際公約となったことで、日本の責任はますます重くなった。電気の3割を石炭火力に頼る日本は、古くて効率の悪い発電所を減らすと言いつつも、いまだに、石炭火力に固執し、2030年度も電気の2割弱をまかなう計画である。不名誉な「化石賞」受賞の根拠である。
日本では、温室効果ガスの約 90% がエネルギー起源からの排出である。エネルギー政策が気候変動対策に直結する。石炭火力からの排出は、90 年代より大幅に増加しており、現在では GHG 全体の約20% に相当し、この間の温室効果ガス排出増の大きな要因となっている。パリ協定の温度目標を達成するためには、日本は現在稼働中の発電所を 2040 年より早く停止していくとともに、その設備利用率を大幅に下げていかなければならない。石炭火力の増設は、パリ協定に沿った排出削減目標と最適コストの排出削減経路からの乖離をさらに拡大するにすぎない愚策である。石炭火力への固執自体が、日本の脱衣炭素化の大きな障害となることは、自明である。
すでに、日本は、2020年の「ゼロカーボン宣言」で、2050年に排出量の実質ゼロを掲げている。削減のペースをあげていくといった計画の策定が求められる。代替電源の確保は容易ではないが、依然として、石炭と原子力に固執汲々としている体たらくは、日本の本気度のなさと、限界を露呈してしまっている。これでは、「羊頭狗肉」と批判されてもいたしかたない。このままでは、日本の将来は暗い。
そもそも、気候変動は、干ばつや豪雨など自然災害の頻発化や激甚化、食糧供給へのリスク増など、世界中のすべての人々の暮らしをおびやかす喫緊の課題であり、特にグローバスサウスと呼ばれている途上国では、脆弱なインフラや気候変動対策の遅れなどから、まさしく人々の命が危険にさらされている。洪水や水不足は、その流域での紛争の火種となりかねない。主たる加害者は、日本を含む先進国である。加害者である先進諸国が、こうした問題意識を共有ができるか否かは、その国が「気候正義(climate justice)」を持っているかに依る。はたして、日本に、この肝心の「気候正義」があるのか?ないのか?
日本の最後の基幹産業とも揶揄されている自動車もしかり。EVの時代が間違いなくやって来ることは自明であるにもかかわらず、世界最大の自動車メーカーだと自負するトヨタは、いまだに、燃料電池車にこだわっている。この固執が、根本的に間違っているし、日本の致命傷になりかねないと、山岡は思った。日本のガラパゴス化の宿痾は、ここまで、深刻なのかと、山岡は、憂鬱な気分になった。
なぜなら水素スタンドには限界があるからである。トヨタは、燃料電池車の成否は、水素スタンドのインフラ整備次第だと言っているが、その設置コストは、一基5億円もかかる。EVスタンドの100倍である、全米でEVスタンドが50万台設置されようとしているときにそれでは、世界のEV化の潮流に対抗できない。いまさら、燃料電池車にこだわっていても、絶対に脱炭素革命の遂行は、不可能なのだ。
EVシフトは、4万社以上ある下請け企業の再編、切り捨てにつながり、返り血を浴びる覚悟がないと踏み切れない大改革だ。同社の市場シェアと収益に壊滅的なダメージを与える可能性がある。このリスクにおびえるトヨタは、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車にFCVとEVという全方位戦略で時間を稼ぎ、その時間でFCVの大幅なコスト削減と、下請け企業の再編を段階的に行っていくソフトランディング策を模索してきた。しかし、欧州委員会は、2035年までにEU域内の新車供給をゼロ・エミッション車に限定するという厳しい政策文書を2021年7月14日に発表した。もはや、待ったなしである。いまや、世界中が、テスラを追いかけている。この中で、日本だけ遅れている。むしろ、逆走している。隣国中国のEVシフトは本格化している。ドイツはじめ欧州各国もそうだ。
はたして、いまの、日本の為政者と企業経営者は、真剣に、7世代先の人類の安寧と幸福を念頭に、判断をしているのであろうか。あるいは、当面の目先の自己保身だけで、できない理由ばかり並べあげて、言い訳の先取りという、もっとも姑息な思考回路に閉じこもってしまっているのであろうか。
先日英国グラスゴーで、エリザベス女王はCOP26に参加した各国首脳に向け「一時的な政治の枠を超え、真のステーツマンシップを」と呼び掛けた。まさにステーツマンシップ無くして地球温暖化問題には解がない。コロナ禍の気候危機時代は、明るい未来を構築する空前絶後の好機である。度重なる異常気象に象徴される気候変動問題や、今回の新型コロナウイルス禍は、自然界と人間社会の調和的バランスの不均衡への人類に対する最後通告だ。気候変動問題が「イエローカード」なら、今回の新型コロナウイルス禍は、性懲りもなく愚行を繰り返してきた人類に対する「待ったなし」の「レッドカード」である。
アフター・コロナ時代を視野に、いまこそ求められるのは、地球市民として人類の「価値変容」と「行動変容」であり、いま人類がとりくむべきは、脱炭素社会(The decarbonized society)構築に向けた「人類社会全体の根本的なアップデート」であり「トランジションデザイン(Transition Design)」の具現化である。はたして、日本には、その「トランジションデザイン」が、あるのか。
いま、あの、戦場において戦士に死を定め、天上の宮殿ヴァルハラへ彼らを連れて行く役目を持つ北欧神話に登場する複数の女神ワルキューレが、日本の上空を、滑降している気がしてならない。はたして、日本は、討ち死にし、死して、このまま天上の宮殿ヴァルハラへ連れ去られてゆく運命なのか。あるいは、女神ワルキューレが、微笑して、日本の未来に、「死」ではなく、「生」につながる、あかるい「希望の光」を与えてくれるのであろうか。
いま、山岡の脳裏には、しきりに、「ワルキューレの騎行」の旋律が、リフレインを始めているのであった。
End Of Documents