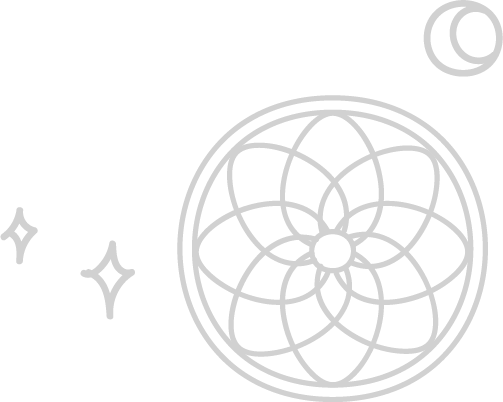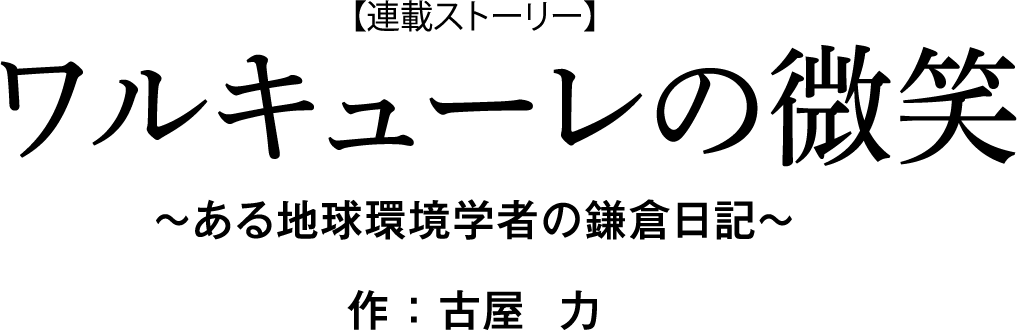
2022.6.21 掲載
ドイツに8年以上も住んでいた割には、山岡家は、結構、隣国フランスには越境訪問を繰り返した。今日は雨。山岡は、静かに病室で本を読んでいた。ふと、『巴里の空の下セーヌは流れる(Sous le Ciel de Paris)』のメロデイーを、なぜか、懐かしく、思い出した。ドレジャック(J. A. Dréjac)作詞、ユベール・ジロー(Hubert Giraud)作曲により作られ、1951年のフランス映画『巴里の空の下セーヌは流れる(Sous le Ciel de Paris)』の挿入歌として、オリジナル版はリーヌ・ルノー(Line Renaud)により歌われた伝説の歌だ。
最初にこの曲を聴いて気に入ってしまったのは、大昔。1980年代。新婚旅行で、英仏2か国訪問の旅の最中であった。当時、すでに、同期親友の五代君が、パリに住んでいた。語学研修生制度で、いわゆるトレイニーとして、フランス語を学び、その後、パリ支店で働いていた。
友達はありがたい。「新婚旅行で、今度、パリに行くよ」と伝えたら、「パリ滞在中はホテルもレストランもすべて引き受けるので、一切、何も準備しないでほしい」との、うれしい問答無用の即答が来た。オペラ座近くのパリ支店で合流し、彼の愛車で、一路、フォンテーヌブロー(Fontainebleau)に。彼の車中でたまたま流れていた曲が、Sous le ciel de Parisであった、愉快なパリ郊外へのドライブだった。この曲を聴くと、いまでも、若かりし頃の、あの愉快なひと時を思い出す。
Sous le ciel de Paris
S'envole une chanson
Hum Hum...
Elle est née d'aujourd'hui
Dans le cœur d'un garçon
Sous le ciel de Paris
Marchent des amoureux
Hum Hum...
彼がアレンジしてくれたフォンテーヌブローのバルビゾン村にも近い小さなレストラン付ホテルは、部屋の調度のセンスも大いに気に入った。ファブリックやアンティークの木製家具を使用したエンパイアスタイルの内装。そして、何よりも最高のフレンチと極上のワインに感動した。友の友情に目頭が熱くなった。
ドイツ時代は、この曲Sous le ciel de Parisが、いつもパリ行きの、トリガーであった。フランクフルトでのいつもの週末、金曜日、夕食後、妻と談笑している最中、ふと、山岡は、妻の目を見て、「どう?これからパリにでも行こうか?」と打診。妻も、「いいわね。」と合意。これが、山岡家の、パリ行きの流儀であった。
2時間後には、ハンドルを握って、愛車のオンボロのベンツでパリに向けてアオトバーンを走っていた。深夜のパリ行きのアオトバーンは、すいていて快適だ。脳裏でSous le ciel de Parisがリフレインしていた。疲労感はない。
フランクフルトを夜中に出発すると、たいてい、セーヌ河畔に日の出のころ到着する。セーヌ河畔の名もないカフェ美味しいカフェオレで目を覚ませて、クロワッサンで朝食。パリを気ままに散策。ホテルは、いつも行き当たりばったり。野暮な予約なんてしない。隣の芝生効果もあるのか、バカンスの度、隣国フランスには越境訪問を繰り返した。特に長い時間が 確保できた時には、ブルゴーニュに足を延ばした。
ブルゴーニュのお気に入りの宿は、Hôtel Restaurant Le Montrachetであった。Le Montrachetは、オーセンティックな19世紀の建物で気に入っている。ボーヌ(Beaune)から12km先にあるピュリニー・モンラッシェ(Puligny-Montrachet)の中心部に位置している。何と言っても、ここの魅力は、美味しワインと上質なグルメ料理。ブルゴーニュのワインの産地を探索するのに理想のロケーションだ。
ブルゴーニュというと、日本では赤を想起する人も多いが、白もあなどれない。特に、この定宿にしていたPuligny-Montrachetの白は、泥灰土や化石を含んだ石灰、堆積物などが複雑に重なり合った複雑な土壌から成る世界最高峰の白ワインとも言われるブルゴーニュのアペラシオンの中でも頂点だ。
Le Montrachet を拠点に、気ままなドライブは至福のひと時だ。温暖な気候と肥沃な土壌に恵まれていることから“フランスの食料庫”の異名をもつ1000km以上に渡って続くブルゴーニュのワイン街道を通って、様々な畑を見て周れる。新鮮な野菜や畜産物を使った料理など豊かな食文化が根づく地域でもある。気取らない本物の伝統料理を堪能しながらワイングラスを傾ければ、心も体も解放される。
「飲むよりも語られる事の方が多いワイン」として、しばしば言及される。かのロマネ・コンティ(Romanée-conti)の畑は、なんと、たったわずか1.814ヘクタールしかない狭い畑だ。最初訪問した時は、そのささやかな規模に驚いた。コンティ公のルイ・フランソワ1世が1760年にこの畑を手に入れたときから、260年間この名前だ。粘土質と石灰質の土壌がバランスよく混ざった「ピノ・ノワール(Pinot noir)のために存在する神の畑」だとも呼ばれている。
(次章に続く)