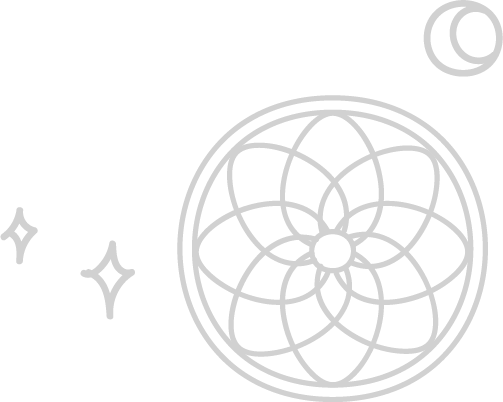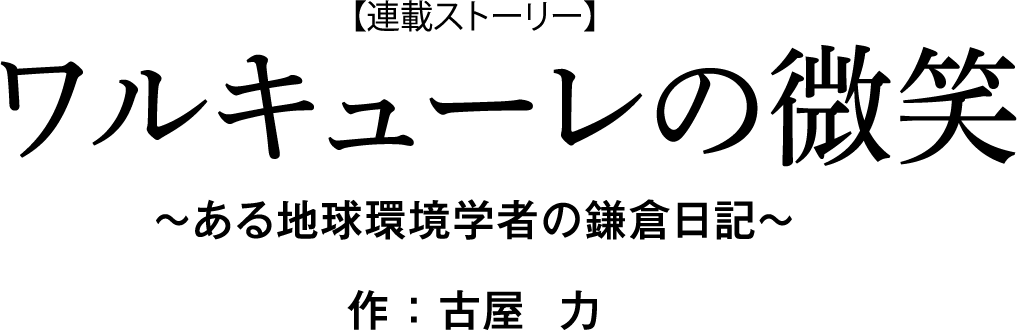
2022.5.10 掲載
熟思黙考するには、このアレグレットが、好い。かたくなに同音が反復されつづける静的な旋律でありながらも、和声的には豊かに彩られているこの深淵な音の世界に浸れる至福。ベートーヴェン(Beethoven)の交響曲 第7番 イ長調 作品92 の第2楽章(Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: II. Allegretto)である。ワーグナーはこの楽章をさして「不滅のアレグレット」と呼んでいる。
本郷の研究室でも、鎌倉の自宅書斎でも、論文を書く前に、静かにこのアレグレットを聴くと、自然と前頭葉が起動を開始する。そして、論文執筆に入る時に、バッハに切り替える。脳の働きと音楽との関係性は詳しくないが、山岡は、いつも、経験則で、音楽と仕事の内容との相性を大切にしてきている。
今、山岡は、病室で、このアレグレットを聴きながら、デイビッド・ウォレス・ウェルズ(David Wallace-Wells)の『地球に住めなくなる日(The Uninhabitable Earth: Life After Warming )』を読みながら、この地球という惑星で始まりつつある価値変容の含意について静かに考えを巡らせている。
これは、気候変動により壊滅的な危機へと向かう近未来を描いた衝撃の警告書である。その中で、平均気温が3.7度上昇した時の経済損失は551兆ドルとなり、世界全体の所得の23%が2100年までに消えると警告している。そして、気候変動が現下の人類経済社会システムを根本的に台無しにする2つの流れを加速させていると分析している。その1つは「経済停滞」。もう1つは「格差」である。
あたかも、新型コロナウイルス禍が、既往病変を重篤化させ短期間に死に至らしめたように、気候変動問題も、現下の資本主義システムの重篤な既往病変をさらに悪化させ、人類経済社会システム自体を死に至らしめるのである。これも人類の自業自得だと言ってしまえばそれまでだが、もはや、気候変動問題が解決しない限り、人類経済社会システムの持続可能性は心もとない。人間には、瀕死の状態に呼吸・循環サポートするECMO(Extra Corporeal Membrane Oxygenation)という救命道具があるが、資本主義システムには、もはやECMOどころか人工呼吸器すらないのである。
それでは、なぜ、人類は、深刻な気候変動問題を認識しておきながら、自らの暴走を制御できないのか?無限ループのような愚かなリスクの増殖を、なぜ、今日まで許容してきてしまったのか?確かに、人類は、あまりに圧倒的かつ広大な気候変動の甚大被害と自らの日常の経済活動との因果律を認識する「解像度」が致命的に欠損している。かつ「実行力」が脆弱である。
しかし、むしろ、気候変動問題の究極の根本原因は、資本主義システムの「増殖」という属性にあると言えよう。本源的に「増殖」という属性により無限装置のように経済成長を志向し駆動し続ける資本主義システムの中で、はたして、この達成困難な気候危機の難問が解決できるのであろうか。すくなくとも、新型コロナウイルス禍対策のような、不可避的な派生としての深刻な経済活動停滞という「我慢比べ」が毎年繰り返されることに人類はもはや耐えられないであろう。
そもそも現下の資本主義システムの本質は、「自己増殖」にあり、持続不能な本質を内包している。この資本主義システムは、利潤のために飽くなき生産と消費の拡大を必要とし、「地球環境」の有限性等をまったく配慮しない強欲な人類の消費に地球環境は耐えられない。指数関数的な生産と消費の爆発の背景にあるのは、ひたすら利潤を求める資本主義の本質があり、それには、もはや限界がある。
それでは、新型コロナウイルス禍を契機に、いかにしたら、人類は、コロナ禍のような「我慢比べ」ではない手段で、快適で持続可能な経済社会システムを担保できる「新しい日常」を構築することが可能なのであろうか?あるいは、それはとうてい実現不可能な絵空事だとして、早々に絶望するしかないのであろうか?
実は、この「解」は、資本主義システムの「増殖」を駆動している「通貨」にあるのではないだろうか。自然物の価値は時間の減少関数であり、人類も減価償却という知恵を持っているが、「通貨」だけは時間の増加関数である。その「通貨」の「増殖」という本質が、忌まわしい病根なのではないか。無限装置のように経済成長を志向し駆動し続ける資本主義システムの「増殖」という属性を抜本的に変えるためには、「通貨」の「増殖」という本質を変えるしかない。そして、その新しい「通貨」の想像が、新しい資本主義の在り方を規定し、この地球という惑星で始まりつつある価値変容を決定つけるのではないかと、そう、山岡は、思った。
そして、かつて「還暦記念旅行」で、訪問したトスカーナのフィレンツェのメディチ家(Medici)を思い出しながら、さらに山岡は、通貨と利子と資本主義の本質と地球環境問題との位相について思索を展開した。その資本主義の本質たる「自己増殖」の根本にあるのが「通貨」と「金利」。資本投下し利潤を得て資本を自己増殖させることが資本主義の本質。その鍵が「通貨」と「金利」。この地球上に存在している万物は腐敗し減価する「時間の減少関数」である。しかし、唯一例外的に「時間の増加関数」である存在がある。それが、「通貨」である。そして「時間の増加関数」であることを担保してているのが「金利」である。本来なら、「通貨」ですら、「時間の減少関数」であるべきである。つまり、元来、「金利」はマイナスが必然当然である。
「通貨」と「金利」の本質的限界を危険を察知していた古代宗教は、かつては、「金利」を否定してきた。かつては、一神教として知られるユダヤ教、キリスト教、イスラム教は、その本質を喝破していた。だから、それぞれ、利息を禁止してきた。イスラム教はいまも建前としては利息を禁止、ユダヤ教は「同胞」に限って禁止し、また、キリスト教は中世末期の宗教改革で詭弁を弄して解禁した。宗教は議論の余地のない教義として巧妙に「収奪阻止装置」を実装してきたのである。
いまや、地理的・物的空間においてフロンティアが消滅し、米国の投資家が作り上げた電子・金融空間も、リーマン・ショックをきっかけに縮小に転じ、利潤率が極端に低く資本が自己増殖しなくなってきている。かつてケインズが定義した「資本の限界効率」がゼロになるのである。その結果、資本主義が資本主義として機能しなくなり、その結果、資本主義は自己増殖の運動をやめ、その役割を終える。その必然の向こうに、はたして、「通貨」と「金利」は、いかなる姿をしているのであろうか?いまや、コロナ禍の気候危機時代において、「通貨」と「金利」を再定義すべき時代をわれわれは迎えているのである。
(次章に続く)