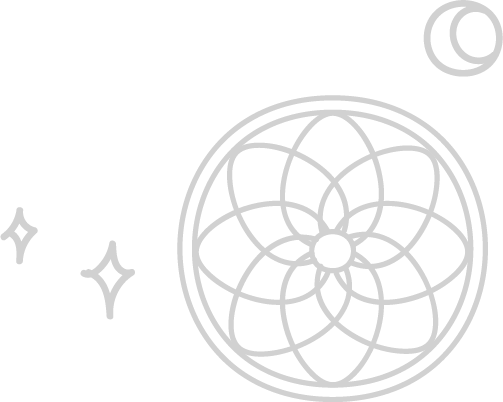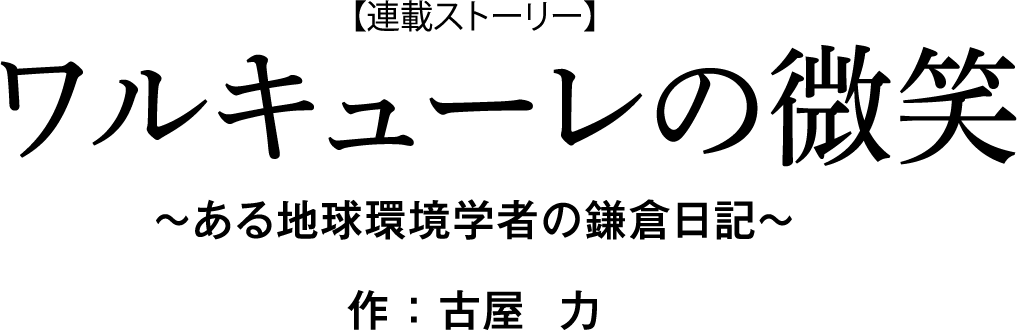
2022.3.22 掲載
鎌倉に、ささやかな戸建てのちっちゃな居を構えたのは、1992年。5年間のドイツ赴任から帰国した年の夏である。「終の棲家」として、思い切って購入した。もうかれこれ30年近くの大昔の35歳の若気の至り!まさに、蛮勇であった。山岡は、ドイツの緑豊かな住環境がとっても気に入っていたので、帰国後、同様な緑豊かな閑静な住環境で、かつ、妻の実家にも近い物件を探した。ようやく、環境的にも予算的にも最適な物件として巡り合ったのが、いま住んでいる鎌倉の辺鄙な山奥の小庵であった。
当時まだ35歳の若輩にとって、予算も限られていたが、通勤時間が長いことを犠牲にして、他の要件を見事に満たしていたこの戸建てを、思い切って購入した。そして、結局、子供も含め、家族全員が気にいった。3人の子供たちにとって、鎌倉が故郷となった。今思えば、結果的に、この判断は正解であった。
当時働き盛りの山岡にとっては、朝から晩まで東京で働き、帰路1時間半かけて鎌倉の山奥の自宅に帰るのは、正直しんどかった。でも、その苦労を凌駕する魅力が、この山奥の小庵にはあった。そして、何よりも、3人の子供たちが、大自然に囲まれた環境を気に入って、友人もでき、すくすく育った。鎌倉の新居の裏山は、紅葉の名所の天園であった。自宅から徒歩3分で、すぐ天園ハイキングコースの登山道であった。子煩悩の山岡は、週末、よく3人の子供たちを引き連れて、天園に登った。海一望の頂上まで、子供のゆっくりとした足でも30分も要らなかった。山頂からは、鎌倉の美しい海が遠望できた。
実は、この裏山散策の際に、山岡と3人の子供たちの間には、1つ阿吽の呼吸の密約があった。それは、リコーダーを持ってゆくことであった。特に、長女が、この密約を気にいっていた。山頂で、妻がつくった手作りの美味しいおにぎりと卵焼きを食べ、海を眺め、そこで、リコーダーを合奏した。四方の山々に、リコーダーアンサンブルの音色が響きあった。特に十八番は、「故郷(ふるさと)」と「春風」であった。秋の紅葉が美しい季節には、まだ東京から一般登山者が来る前に、紅葉の絨毯を独り占めして、紅葉谷にリコーダーアンサンブルの「赤とんぼ」の音色が響き渡った。
実は、山岡自身とリコーダーのご縁も古い。小学校時代から、リコーダーが大好きだった山岡が、中学校時代、音楽教師の望月先生にリコーダー演奏を、いたく褒められたことがあった。人間と言うのは、褒められると、ますます好きになるものである。そして、みんなの前でベートーヴェンの第九交響曲の第4楽章の「歓喜に寄す」部分を演奏するように指示を受けた。全員の前で演奏することは初体験であった。しかし、演奏後の万雷の拍手がうれしかった、先生も友達もほめてくれたので、ますます、山岡は、リコーダーが大好きになった。
高校時代は、まさに、別の意味でリコーダーの名手として、有名になった。というのも、友人の強い推薦で、生徒会長選挙に立候補して、見ごと当選したことがあった。悩みは、生徒総会だった。生徒会長のあいさつの際に、どうも、みんなを惹きつける何かが不足していた。そこで、リコーダーが登場した。思い切って、生徒会長のあいさつの際に、はじめに、リコーダーを演奏したのだ。この突拍子もないリコーダー演奏に、最初は度肝を抜かれ唖然としていた生徒諸君も、演奏後は、万雷の拍手が起こった。まさに奇跡の瞬間であった。以降、挨拶の内容より、次は何を演奏するかが注目されるようになった。
こうしたリコーダーの不思議な物語は、その後も、どんどん、フーガのように、進化発展してゆく。大学に進学し、書生として汗かいて働いて貯めたお金で、ヨーロッパに貧乏旅行したことがあった。多言語の欧州で、出会う人々にいかにしてコミュニケーションするかが、課題であった、語学の天才でもない山岡が、秘密兵器としてリュックサックに忍ばせたのが、1本のソプラノ・リコーダーであった、苦肉の策であった、
そして、作戦は、見事、的中した。横浜港からソ連船で2泊のナホトカまでの船中で、そして、モスクワに向かう1週間のシベリア鉄道で、さらには、モスクワの赤の広場で、レニングラードの街角で、最初の欧州の街ヘルシンキで、山岡は、リコーダーを演奏した。大好評だった。コミュニケーション手段は、何も言語だけではなかった。音楽は国境を越え、イデオロギーを超えた。そして、その成功体験に気をよくした山岡は、続く、ストックホルム、コペンハーゲン、フランクフルト、ミュンヘン、等々、西ヨーロッパの都市の街角で、リコーダーを演奏した。
感動的な珠玉のシーンがある。パリのノートルダム寺院前の広場で、リコーダーを演奏した時の出来事であった。いつも通り、日本の、「故郷(ふるさと)」「赤とんぼ」から始まり、十八番のビートルズの「イエスタディ」から「ヘイ・ジュード」に移った時、忘れえない想定外のハプニングが、起こった。山岡を囲んでいた老若男女が、一斉に「ヘイ・ジュード」の大合唱を始めたのである。世界中からパリを訪問していた様々な国籍の人々が1つになった瞬間であった。山岡は、このすごい大合唱の洗礼に、大いに感動し、演奏しながら、泣いていた。その後も、様々なお国言葉で、素晴らしいみなさんの歌も披露されて、忘れがたいパリの夜となった。
たった1本の何の変哲もないリコーダーが、かくも世界中の人々の心を1つにすることを実体験でき、それが、山岡の人生に、大きな影響を与えた。言語や、肌の色や、宗教や、イデオロギー等々、様々な違いを乗り越えて、音楽を通じて、人類は1つになれる。そう確信をもった瞬間であった。余談ながら、このリコーダーの不思議な物語は、その後も続く。実は、いまの本郷での勤務先大学の講義でも、初回講義で、山岡は、パリの夜のエピソードを前振り説明して、リコーダーで1曲演奏してから、講義に入ることにしている。効果てきめん。困るのは、学生からのリクエストが後を絶たない点である。
大学教授を退縮する時の最終講義では、「故郷(ふるさと)」を、愛用のリコーダーで、サプライズで、大好きな学生諸君に贈ろうかと、静かに企てている。
(次章に続く)