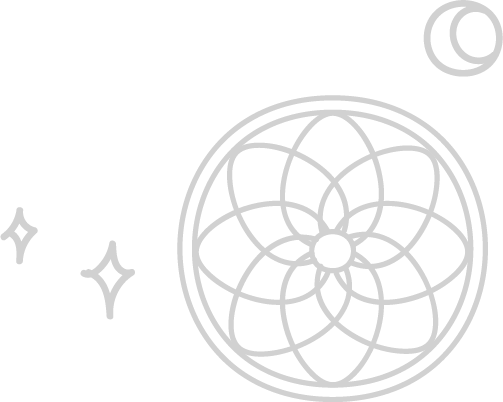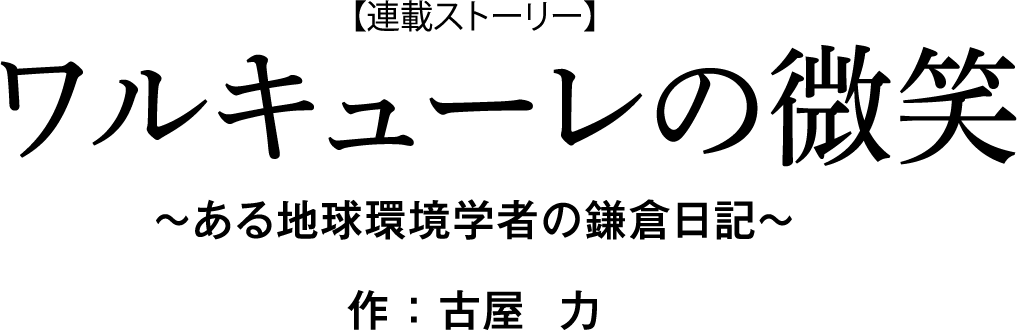
2022.8.16 掲載
ついに、山岡に、声が復活した。
気管切開期間が無事終わり、気管縫合手術をした。全身麻酔の本手術と違い、局所麻酔なので、1時間程度の手術の最中、主治医や助手、看護師の言動が、まさに、実況中継で把握でき、面白かった。縫合手術自体は、さほど苦痛もなく、無事終了。山岡は、そのまま歩いて自力で病室に戻った。
むしろ問題は、縫合手術後退院までの1週間の「絶対沈黙」指示であった。もうあらゆるチューブから解放され、後は退院を待つ自由な身ではあるが、自由解放の喜びと裏腹に、この最後の卒業プロセスの「絶対沈黙」の苦行は、なかなかやっかいであった。いまではもう、自然と声が出せる状態だけに、縫合手術の傷口を配慮した「一切声を出してはならぬ」という、この「絶対沈黙」の厳命は、むしろ、結構の難行であった。できるのに、してはならない、この厳命に、山岡は、何やら修道僧にでもなったような気分になった。
「絶対沈黙」という厳命を聴いて、山岡は、ふと、サイモンとガーファンクルの「サウンド・オブ・サイレンス(The Sound of Silence)」を思い出した。サイモンとガーファンクルと言っても、いまの学生諸君で知ってるものはいない。山岡の世代に一斉を風靡したミュージシャンであり楽曲である。全米1位を記録したこの不朽の名曲は、山岡の世代にとって、知らない人はいない伝説の名曲であるが、むしろ、いまの学生にとっては、いまから半世紀も大昔の1967年のアメリカ映画『卒業』で挿入曲となったことで、この名作映画の曲として、聴いたことがある方々も多いのかもしれない。
Hello darkness, my old friend
I’ve come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
やぁ暗闇 我が懐かしき友よ また君と話しに来たんだ
なぜかって 予見さ ふとひらめき 残された種 僕が寝ている間に
“Fools”, said I, “You do not know
Silence like a cancer grows
Hear my words
that I might teach you
Take my arms
that I might reach you”
「愚か者たちよ」僕は言った 君たちは知らない 静寂は癌のように広がる事を
聞いてくれ 僕の言葉を 君らへ伝えるから 僕の腕をつかんで 君らへ届かせるから
そもそも、この「sound of silence」という言葉は、1960年代のアメリカにおけるカウンターカルチャー運動の中で誕生した、時代の空気感を象徴する伝説の曲だ。当時の大国アメリカの大きな政府に対する不信感や、運動の担い手である若者らが既存社会に対して抱く疎外感などの象徴として用いられていた。そもそも、カウンターカルチャーとは、既存の価値観や行動規範に基づく主流社会の文化であるメインカルチャーとは大きく異なる、それら主流の文化的慣習に反する対抗文化であった。1960年代のアメリカにおけるカウンターカルチャーの流れ。ヒッピーやロック、反戦運動、公民権運動などが代表的である。
いまやコロナ禍の気候危機時代という、未曽有のパラダイムシフトの時代に、人類は、いやがおうでも、突入してしまっている。旧来型の価値観や行動様式が、ことごとく否定され、この地球という惑星上の77億人の人類が、「誰一人取り残されることなく」価値変容と行動変容を余儀なくされている。山岡は、この時代こそ、「sound of silence」の響きが、ふたたび、必要な時代なのではとふと思った。単なる夢想ではあるが、この地球に、気候危機の最中に突如登場した今回の新型コロナウイルスは、宇宙から送られた新種の「最後通告(Ultimatum)」かもしれないと思った。
新型コロナウイルス感染症と気候危機は致命的な危機だ。人類の生存に関わる深刻な連帯問題だ。いま、人類は、容易ならざる深刻な実情に直面している。それにもかかわらず、いまだに、人類は、この期に及んでも危機感を共有できず、思い切った行動に踏み込めないでいる。
6年前の2015年にようやく誕生した起死回生策の「パリ協定」も「SDGs」も、為政者の威勢のよい宣言とは裏腹に、いまだに、その進捗状況は、はかばかしくなく、コロナ禍が問題を悪化させている。脱炭素で持続可能な社会への速やかな移行を進めることが世界が目指すべき方向であることは自明だが、それが、できていない。家の中で火事が起こっているのに、消火できていないばかりか、よせばよいのに、儲け目当てで、姑息なことに、まだ燃料をつぎ込もうとしている愚かな人々すらいる始末だ。今、人類は、人間活動が地球環境に大きな影響を与える時代「人新世(Anthropocene)」にいる。そして、もはや不可逆的でとりかえしのつかない危険な転換点(tipping point)に立っている。もう、待ったなしです。いままでの対処療法では、埒があかない。根本治療が急務だ。
それでは、はたして、根本治療すべき「宿痾」の根本原因は何なのか?この地球と言う惑星上の、戦争や人種差別、性差別、過剰な交通、大気汚染、人工的な食物、貨幣制度、経済格差等々、課題山積で、実に忌まわしくやっかいな「宿痾」の根本原因は、実は、「通貨」ではないかと、山岡は、考えている。
実は、かつて、すでに、このことに気づいていた存在があった。それは、宗教であった。人類は、その長い歴史の中で、人が地球環境への加害者とならないための仕掛けとして、果てしなき貪欲な振る舞いを抑制する巧妙な仕組みを、宗教というプラット・ホームに実装してきた。同源の一神教として知られる古代キリスト教や、ユダヤ教、イスラム教に底通している「金利を禁止する教義」がそれだ。イスラム教が、「リバー」つまり増殖(利子)を禁止していることは周知の事実だ。このリバーとは、「増殖する」という意味のアラビア語ラバー(ربا rabā)から派生した語で、単なる利子の概念よりも広い範囲く、不労所得として得られる利益等すべての貪欲な振る舞いに対する抑止となった。
それでは、そもそも「金利」とは、何か?専門家のやや小難しい解説では、「異時点間交換にともなう差額の補填」であるとの説明もある。信用システムから必然的に生じる利潤が金利だと。その金利追求こそが、現代資本主義の根幹であり、同時に、諸問題の元凶でもあった。
「金利」を前提とした「古い通貨」の仕組みは、とっても深刻な「副反応」がありました。この「古い通貨」の仕組みによって、休むことなく馬車馬のように走り続け、経済の拡大・成長を追求することを運命づけられた疲弊した社会になった。さらに、その「副反応」は、人々を疲弊させるだけではなく、「成長神話」という一種の「共同幻想」に人類を巻き込み、忌まわしき「無限ループ」の呪縛に人類は洗脳されていった。そして、大量生産・大量消費・大量廃棄を人類に強い、その結果、地球環境は汚染され、破壊され、人々の信頼や団欒を毀損し、不条理な格差を生み、性懲りもなく繰り返し忌まわしき戦争が起こった。
そもそも、「金利」は、人類が作り出した一種の「共同幻想」ではないかと、山岡は思っている。自然界は、木も花も、一般に時間の経過とともに減価し、朽ちてゆく。金利のように時間の増加関数は、自然界にはない。むろん、通貨自体は、便利で有益な知恵にちがいない。通貨には、本来、暮らしに役立つモノやサービスと交換したときにその価値を図る「価値尺度機能」と交換の媒介としての「交換機能(決済機能)」と「価値保存機能」がある。通貨は、モノやサービスという効用の代理物で、効用を数値化したシンボルだ。リンゴ1個の価値は腐敗すれば消滅するが、通貨に換えておけば、リンゴ1個の価値を蓄蔵でき、将来リンゴ1個が入手可能となる。
しかし、やっかいな問題は、通貨の属性である「金利」の方にあった。そこに危険が内包していた。諸宗教が「金利」を禁止したのは、通貨が「金利」を纏うことで、本来の効用を離れ、暴走し、増殖し、未来を侵食し、人々を不幸にする畏れがあったからだった。
そもそも「金利」の原資は、物質的生産から得られる利潤の一部だ。したがって資本は永遠に生産に投資し続けざるをえない。資本は、海外市場展開や新製品開発を通じてフロンティアを拡大し、一方で原料コストや労賃の引き下げなどをして利潤追求する。資本の蓄積が進むにつれて、利潤は減衰し、成長は鈍化し、市場も閉塞化し、経済成長は次第に停滞する。成熟した時代になるにしたがって、過剰資本と過剰蓄積が生まれ、投資しても利潤が得られず、利子率はさらに下がっていき、利潤が上がらなければ、金利はゼロに近づく。やがて、市場が飽和し、新製品がなくなり、コスト削減がそれ以上進まず、利潤率は下がり、経済成長は停滞し、不可避的に「成長の限界」の時が来る。資本主義システムの安楽死は、必然的帰結なのだ。
しかし、人類は、生きなければならない。資本主義システムの安楽死を座して待つ訳にもいかない。方や、人類の眼前には、喫緊の課題である気候変動問題等の地球環境問題がある。では、どうしたらいいのか?はたして、資本主義システムを安楽死させずに、人類の社会経済システムの持続可能性を担保しながら、同時に、地球環境問題を解決できるような、そんな優れた処方箋なんてあるのだろうか?
(次章に続く)