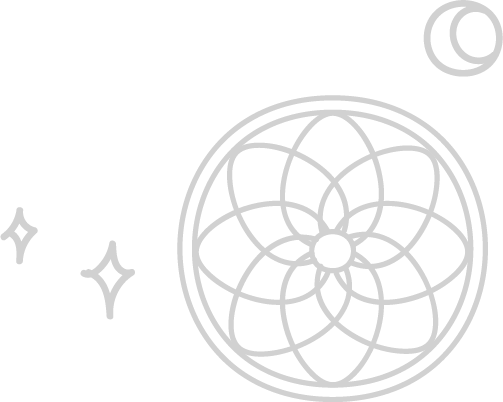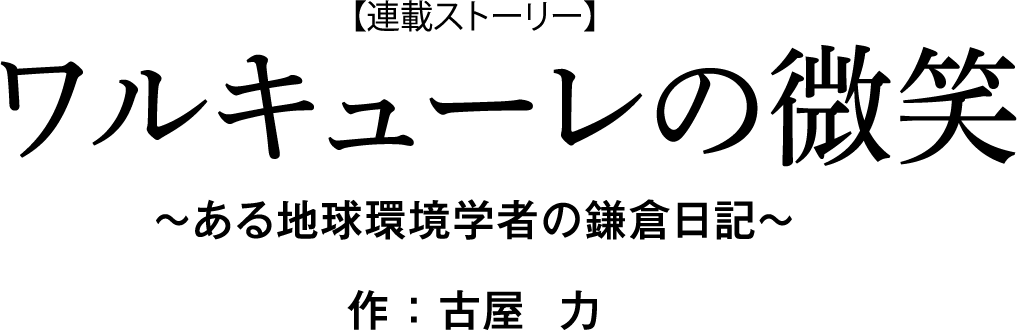
2022.5.17 掲載
思えば、在欧時代、夏やイースター等の様々なバカンスで、山岡は、家族と、ほぼ欧州全土を訪問したが、とりわけ、南仏ほど、優しい香りと豊潤さに包まれた旅はなかった。マルセイユ、アルル、アンティーブ、ニース、モナコ、エクサン‐プロバンス、モンペリエ、エズ、カーニュシュルメール、グラース、サントロペ、ポン・デュ・ガール等々、訪問した街のそれぞれが、実に個性あふれる抒情性と、懐かしい優しい香りに包まれ、追憶に誘う。なかでも、忘れがたい街はアルル(Arles)であった。紀元前6世紀頃ギリシア人によって"Theline"の名前で創設された南仏の古都。紀元前535年にケルト人のSalluviiによって占領されたた時、街の名前を 湖の近くの意味であるアレラーテ(Arelate)に変更したのが、現在のアルルの名前の由縁。
中学校時代によく演奏したあのビゼーの名曲『アルルの女(L'Arlésienne)』の「アルル」って、はたして、どんな街なのだろうか、生涯で、一度くらいは訪問することができるのだろうか、と思っていた憧れの街である。あの頃から、アルフォンス・ドーデの小説『アルルの女』に舞台に想像をはせた。初めてアルルを家族と訪問した時は、さすがに、うれしかった。主人公の南フランス豪農の息子フレデリが、アルルの闘牛場で見かけた女性に心を奪われてしまった物語の舞台であった闘牛場(Arles Amphitheatre)も実際に訪問した時には、感無量であった。
ホテルは、以前から生涯1度は、泊まりたいと思っていたHôtel & Spa Jules Césarに数日滞在した。カルメル会の女子修道院だった風情ある老舗ホテルだった。今でも、気に入って購入したこのホテルで使っていたカップ&ソーサ―を、鎌倉の自宅で愛用してる。ちなみに、1888年9月にフィンセント・ファン・ゴッホによって描かれた絵画『夜のカフェテラス』(Terrasse du café le soir)の実際の舞台、カフェプラス・デュ・フォルム広場に面している「カフェ・ファン・ゴッホ」にも行ってみた。
美術研究家ジャレッド・バクスターは、『夜のカフェテラス』はレオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』を参照しているという説を唱えているが、訪問した際にそのカフェでいただいた赤ワインが美いしく、山岡は、その仮説に思いをめぐらす余地はなかった、なお、アルルが、フランス最大面積を持つコミューン(commune)であることは、日本では、あまり知られていない。コミューンとは、フランスにおける基礎自治体、すなわち地方自治体の最小単位である。
いま、山岡が研究しているテーマに、気候危機と共同体の研究がある。企業活動も国家活動も、基本的には、地球環境問題の解決には無力である。短期的かつ利己的な属性ゆえ、むしろ、人間を自然を傷つけ根本的に疎外する原因すら作り出してしまっている。共犯的な加害者である企業や国家は、その属性ゆえ解決者になれない。したがって、気候変動問題等の多くの地球環境問題に対峙するには、短期的かつ利己的な属性を内包する国家を前提とした現下のしくみでは解決が困難である。そのとどめの一発が、国家の微力さを露呈させ、現在世界中の77億人の人類を戦慄させている、新型コロナウイルス禍である。
経済学の父と呼ばれたアダム・スミス(Adam Smith)は、かつて、こう洞察している。
「賢人は、最低水準の富さえあれば、それ以上の富の増加は自分の幸福に何の影響をもたらさないと考える。一方で、弱い人は、最低水準の富を得た後も、富の増加は幸福を増大すると錯覚している。生活の快適さが増すとともに他人からの称賛が得られると思っているからである。しかし、豪華な食事も、美しい衣装も、立派な邸宅も、実際に手に入れてみると愛玩物にすぎず、これらを管理しなければならない煩わしさを私たちに背負わせるだけであることがわかる」。
富の増加は、一定水準までは、人々の幸福を担保するが、一定水準を過ぎると、かえって人々は、不幸になる。むしろ、そこで、必要なのは、利他心である。そして、個々人の幸福や効用の最大化ではなく、有限な富をいかに、互いに、いさかいなく、分かち合うかが、大事になる。利己の追及には限界がある。元来利己的な自己増殖を宿痾とする企業も、またその集合体たる国家にも、利己の追及の先には、破綻しかない。その先に、気候変動問題等の多くの地球環境問題がある。真の持続可能性を担保するのは、利己の追及ではなく、利他心に裏打ちされた「定常型社会」である。
地球環境問題解決のために、そこで国家に代わって登場するのが、国連や国際的NGO活動等の国際的な連携である。いまや、COP等の国際会議でもNGO活動等の「非国家アクター」が主導する枠組みの役割も拡大している。
ドイツ語で、ゲマインシャフト(Gemeinschaft)は「共同体(共同体組織)」を意味し、ゲゼルシャフト(Gesellschaft)は概ね「社会(機能体組織、利益社会)」を意味する。テンニースが提唱したこのゲゼルシャフトとゲマインシャフトとは対概念であり、原始的伝統的共同体社会(共同体組織)を離れて、近代国家・会社・大都市のような利害関係に基づき機能面を重視して人為的に作られた利益社会(機能体組織)を近代社会の特徴であるとする。しかし、山岡は、むしろ、このゲマインシャフトにこそ、気候危機問題解決のヒントがあると、考えている。
日本においては、労働集約型の農業を基礎に「協働型社会」とも呼べるものが形成されていたと言われる。これは産業革命、工業化のプロセスに従って企業共同体へと変貌したと言われる。しかし、バブル崩壊、経済のグローバル化、終身雇用制の崩壊、派遣労働者の採用の増加等に伴い、日本の企業風土も1990年代以降大きく変貌した。
コロナ禍の気候危機時代にめざすは、経済成長を絶対的な目標としなくても十分な豊かさが達成されていく社会である持続可能な「定常型社会」である。こうした文脈で、いま、山岡は、その非国家アクターの重要なアクターとして、共同体に注目している。
(次章に続く)