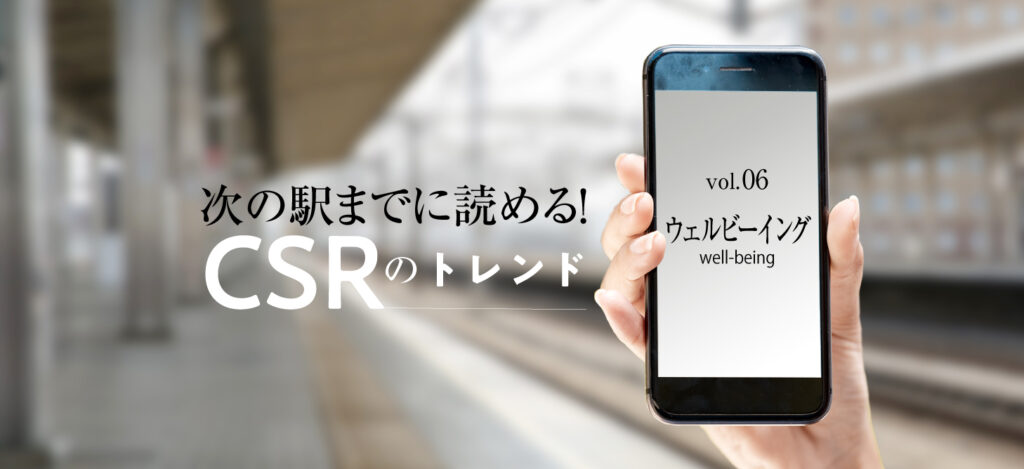

ウェルビーイングとは?
よい(well)+状態(being)という言葉からなり、個人の心や身体と社会が共によい状態で満たされていることを意味する。WHOは「Well-beingとは、個人や社会が経験するポジティブな状態のことである。健康と同様、日常生活の資源であり、社会的、経済的、環境的条件によって決定される。」と定義。以前は社会福祉や医療関連の分野で使用されていたが、働き方改革や新型コロナウイルスの感染拡大による影響で、ビジネスシーンでも使われるようになった。
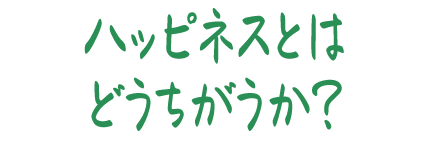
ハッピネスとはどうちがうか?
ウェルビーイングの概念は幸福という言葉に近い。ただ、それはハピネス(happiness)とはちがう。ハピネスは一時的な幸福の感情を指し、ウェルビーイングは、よい状態を表すため、持続的という面で異なる。
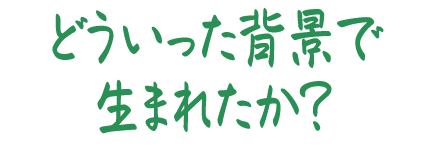
どういった背景で生まれたか?
国連の「持続可能開発ソリューションネットワーク」が毎年発行している世界各国の幸福度を調査した「世界幸福度報告」で日本の幸福度ランキングは低迷。2024年は、対象国143か国の中で51位に位置している。GDP(国内総生産)は、決して低くはなく、経済活動状況が幸福度に直結していないことがここからわかり、日本の幸福度の向上に意識が向き、真の幸福を求めるウェルビーイングの概念に注目が集まっているといえる。

GDPを補う新たな指標「GDW」
ウェルビーイングの概念が浸透する中で、新たな豊かさを示す指標として注目されているのがGDW(国内総充実/Gross Domestic Well-being)。GDPが量的拡大を目指し、物質的な豊かさを測る指標であったのに対して、GDWは質的向上をねらい、実感できる豊かさを測定。既存のGDP(国内総生産)では捉えきれていない、国民の幸福や環境の健全性など、より包括的な豊かさの指標となる。










