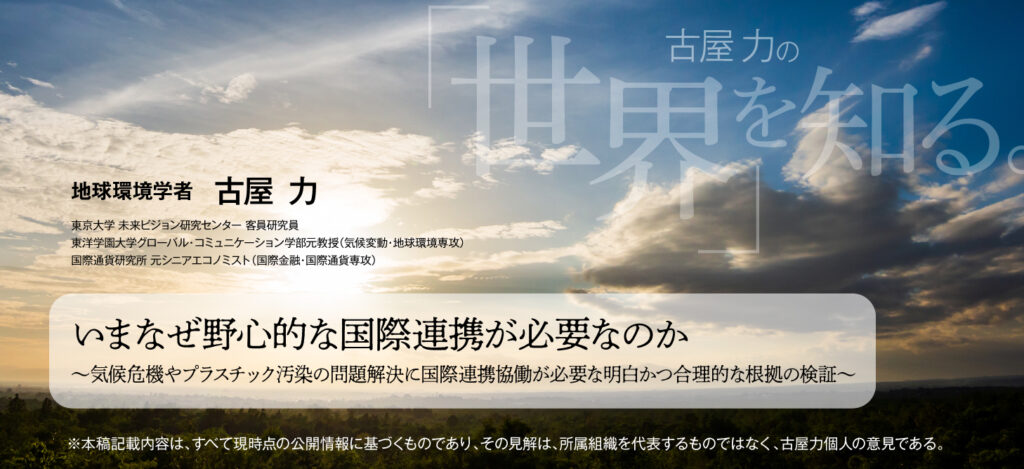
「後にはただ極楽の蜘蛛の糸が、きらきらと細く光りながら、
月も星もない空の中途に、短く垂れているばかりでございます。」
(芥川龍之介『蜘蛛の糸』)
1. 「カンダタ」の含意
もう半世紀も昔の話ではあるが、小学生時代に芥川龍之介の『蜘蛛の糸』を読んだ
殺人や放火、強盗などあらゆる悪行に手を染め、死後は血の池地獄に落ちた罪人カンダタは、地獄で苦しみながら毎日を過ごしているが、生前に一度だけ、蜘蛛を殺さず助けたことがある。極楽の散歩中、蓮池を覗き見た釈迦は、苦しみもがくカンダタを見つけた。そして彼が一度だけ林で小さな蜘蛛を踏み殺さず助けたという善行を行ったことを思い出す。そこで、釈迦はカンダタを助けてあげようと思い、彼にめがけて一本の蜘蛛の糸を垂らした。カンダタは、早速、細い糸につかまって地獄から脱出しようと地上めがけて登りだした。しかし、ふと疲れて下を見ると数人の罪人たちが自分の下で糸をつかんで登ろうとしている。ただでさえ細い蜘蛛の糸、こんなに大人数でつかんでいたのでは途中で切れてしまうと思ったカンダタは、下の罪人たちに「この蜘蛛の糸はおれのものだぞ。下りろ。」と怒鳴った。その瞬間、糸はカンダタの真上で途切れてしまい、結局彼は地獄の底へ堕ちて行った。お釈迦さまは、自分だけが助かろうとしまた地獄へ堕ちていったカンダタを浅ましく思い、悲しみの中、蓮池から立ち去った。
(芥川龍之介の『蜘蛛の糸』)
いまや、「分断の時代」と言われている。そして、「自国第一主義」といった言葉がいたるところから聴こえてきている。「自分さえよければいい」といったカンダタのような考え方をする人も増えてきている。そして、残念なことに、「利他」より「利己」を優先する風潮が蔓延しつつある。
国際社会においても、気候危機問題やプラスチック汚染問題といった全人類に関わる地球規模の喫緊の課題解決においても、自国の都合や利害を優先して、みんなで協力して問題解決に向かおうとする国際連携協働に対して、消極的あるいは否定的な意見も多々側聞するようになった。
しかし、カンダタのような生き方では、結局、あまりよい結果は得れないことは自明である。各国が独自で個別に取り組むより、国際連携協働の方が、最終的に、個々の国々が享受できる便益が大きいことはすでに多くの先行研究で検証されている。国際連携協働の否定には、正当性はない。
「分断の時代」における人類の所作の在り方を考えるべく、以下、あらためて、いま人類にとってなぜ野心的な国際連携協働が必要なのか、その合理的根拠について、論点整理をしてみたい。
2.「NIMBY」と「情報の非対称性問題(Information asymmetry)」
「NIMBY」という言葉がある。「not in my back yard(私の家の裏には御免)」という語句の頭字語である。「総論として対策の必要性自体は容認するが、だからと言って、自らにとって不都合な場所には建てないでくれ」と主張する住民たちや、そのカンダタ的な「自分さえよければいい」といった考え方や態度を揶揄する言葉である。ゴミ集積場所問題や原発建設問題、軍事基地問題等も同様であるが、地元住民が自分たちの地域に提案されたインフラ開発に対して、自らが被る不快感やリスクやコスト等を理由に反対することが多い。そのような住民は、開発が自分たちの近くにあるからこそ反対しているのであり、もしそれがもっと遠くに建設されるのであれば容認したり支持したりする[1]。
気候危機問題やプラスチック汚染問題といった全人類に関わる地球規模課題は、この「NIMBY」の問題に通底する。「総論は賛成だが、自分でコストやリスクを負担するはなるべく避けたい」といった「自分さえよければいい」といった「利己」と「他己」の葛藤の問題を孕むことが多く、なかなか国際協働が思うように前進しない場面が多くある。いずれも一国による対応だけでは不十分であり、野心的かつ制度的に保証された国際協働が必要不可欠であるが、多くの国際会議では、とかく議論が難航する光景が散見されている。
この問題は、「全体最適」の視座の致命的欠落という問題であると言うこともできる。全球的な課題に取り組む政策分野において、時空ともに全球的な「全体最適」に近づける視座が、そしてそのための議論や努力が、ともに、致命的に欠落していることはまま散見されている。しかも、その事態の深刻さが情報として共有されていない。
このことは、二重の意味で、深刻な「情報の非対称性問題(Information asymmetry)」であるとも言える。グローバルな全球的空間において、「全体最適」が自国にとって最終的な最善であるという「情報」が正確かつ十分に共有されていない、つまり「内部化」されていない問題である。それによって、「局所的部分最適」に安住し「刹那的部分最適」を正当化してしまっている事例は枚挙に暇はない。何が「全体最適」なのかを考える一般均衡論的な理論的枠組みも、その考えを実装する仕組みも、「全体最適解」を実現する気概を醸成する風土すらもなかなか確立できてこなかったつけが、いまこうして、気候危機問題やプラスチック汚染問題といった深刻な地球環境問題として顕在化してきているのである。事態はことの他、深刻なのである。
いま、人類に求められているものは、個々の国家が「全体最適」の視座を実装して、環境の変化をいち早く感知し、そこに新しい機会を見出し、それを捕捉して絶えず自己変容していく動態能力、つまり「ダイナミック・ケイパビリティ(Dynamic capability)」[2]である。そしていま「ダイナミック・ケイパビリティ」の不全の問題をいかに解決するかが喫緊の課題となっているのである。
[1] こういった考え方は、「ニンビズム(nimbyism)」とも呼ばれている。また、「ニンビズム(nimbyism)」に対する反対の運動は、「yes in my back yard(私の裏庭ではいいよ)」の略である「YIMBY」として知られている。
[2] 「ダイナミック・ケイパビリティ(Dynamic capability)」は、環境や状況の変化に応じて、自らの資産・資源・知識を再構成し再配置しながら自己を変革する能力を意味する。
3.野心的な国際連携協働が必要な明白かつ合理的な理由
人類が、気候危機問題やプラスチック汚染問題といった深刻な地球環境問題に対して、「ダイナミック・ケイパビリティ」の不全の問題を解決し「全体最適」の視座をもって、環境の変化をいち早く感知し、そこに新しい機会を見出し、それを捕捉して絶えず自己変容していくためには、グローバルなコンセンサスとそれを実現するための野心的な国際連携の仕組みが必要である。そのため、いままで「パリ協定(Paris Agreement)」や「SDGs」さらには「国際プラスチック条約(The Global Plastics Treaty)」等、様々な国際的枠組み造りのチャレンジが展開されてきた。しかし、なかなか、思うように進んでいないのが悩ましい実態である。
その足かせとなってきた背景には、各国が、国際連携協働の必要性について、その明白かつ合理的な理由について、十分、共有化、内部化、納得してこなかった事情がある。「全体最適が自国にとって最善である」という情報が正確かつ十分に共有されてこなかったのである。総論賛成しながらも、各国は「自国でコストとリスクを負担してまでやる必要性」について十分納得せず「自国の問題」として「内部化」してこなかったという「情報の非対称性問題」があった。
この「情報の非対称性問題」を解決するためには、国際連携協働の合理的な理由について認識を共有する必要がある。このための説得力をもって客観的に説明できうる材料は、過去の先行研究等で、科学的知見に裏づけられた明白かつ合理的な理由が検証されている。
気候危機問題やプラスチック汚染問題といった地球規模課題に取り組む野心的国際連携協働がなぜ必要なのかという、そもそもの本源的な問いについて、過去の先行研究によって様々な検証がされ、その正当性や合理的根拠が示されてきたが、その主な合理的根拠としては、以下5点を挙げることができる。
【野心的な国際連携協働が必要な明白かつ合理的な理由】
●「外部性(Externality)」・「越境性」・「グローバル・コモンズ(Global Commons)性」
気候危機では、温室効果ガス(以下GHGと略)は国境を越えて大気中に蓄積し、排出源の所在に関わらず全地球的に影響を及ぼす。また、プラスチック汚染は、廃棄物は海洋循環や河川を通じて国境を越え、マイクロプラスチックとして全海洋に拡散する。いずれも大気・海洋・生態系といったグローバル・コモンズ[3]を毀損するため、一国的対応では汚染を封じ込めることは事実上まったく不可能である。
●「フリーライダー(free rider)問題」の存在
GHG排出削減やプラスチック規制にはコストがかかるため、各国が「他国に任せればよい」と考える誘因がある。そして、他のメンバーの努力にただ乗りし自身の貢献を怠る「フリーライダー問題」[4]が生じる。その結果、協調が欠如する。そしてGHG排出や汚染が抑えられず、被害は拡大する「全体として非効率」が発生する。それは、最終的に個々の国にとっても不合理な結果となる。よって、制度的に拘束力のある国際協働が不可欠となる。
●科学的知見に基づく「不可逆的リスク」
気候変動問題については、IPCC報告書[5]は、産業革命前からの気温上昇が1.5℃を超えると、生態系崩壊や極端気象の増加など「不可逆的影響」が高まると警告している。また、プラスチック汚染問題については、UNEP[6]や科学誌 Science の報告では、2050年までに海洋プラスチックが魚類重量を上回る可能性や、マイクロプラスチックが人間の循環器系や胎盤にまで検出されるリスクが指摘されている。科学的コンセンサスとして、対策の遅延は「臨界点の突破」につながるため、迅速かつ大規模な国際協働が正当化される。
●不平等な影響と「共通だが差異ある責任」原則
気候危機・プラスチック汚染の被害は、途上国や小島嶼国など脆弱な地域に集中する。しかし、主要な原因は先進国の産業活動と大量消費に起因する。科学的データと歴史的責任を踏まえれば、制度的に公平性を担保した国際協働が不可欠である。
●「予防原則(Precautionary Principle)」
気候危機による災害・農業損失や、プラスチック汚染による観光・漁業への被害コストは、対策費用を大幅に上回ると多数の先行研究が示している。「予防原則」[7]に基づけば、環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼす仮説上の恐れがある場合、科学的に因果関係が十分証明されない状況であっても、あらかじめ全球的な規制措置をとることには、正当性があり、仮にそのリスクの発生可能性に不確実性があったにしても、それは、国際連携協働の不作為や取り組みの遅延を正当化する根拠にはならない。
要は、気候危機問題やプラスチック汚染問題といった地球規模課題は、外部性、越境性を属性としたグローバル・コモンズを毀損する深刻な全球的な喫緊の課題であり、常に不可避的にフリーライダーが発生することで全体として非効率が発生するが生じるリスクがあり、制度的に公平性を担保する必要性からも、「予防原則」の観点からも、その問題解決に対しては、個々の国家が一国の独自の裁量で対応だけでは不十分であり、野心的な国際連携協働の方が合理的であり、必要不可欠なのである。
各国が個別に、自己の裁量で気候危機やプラスチック環境汚染等の問題に取り組む場合よりも、むしろ、みんなで一致団結して国際的に調和のとれたルールを基盤とした国際連携協働によって地球全体で環境問題の大幅改善に取り組む方が、最終的に、個々の国家にとっても経済合理性が大きいのである[8]。
[3] グローバル・コモンズ(Global Commons)は、人類全体で共有する資産や国際的な公共財のこと。具体的には、地球環境や生態系、公海、宇宙、サイバー空間などが含まれる。これらの資源は、特定の国の管轄権が及ばないため、国際的な協力と管理が必要である。
[4] 「フリーライダー問題」は、組織内やコミュニティー内で、他のメンバーの努力にただ乗りし、自身の貢献を怠る行為を指す。「フリーライダー」とは、直訳すると「ただ乗りする人」という意味で、この問題は、組織やコミュニティー全体の生産性低下や士気低下を招き、健全な組織やコミュニティーの運営を阻害する要因となる。
[5] IPCCは、世界気象機関(WMO)および国連環境計画(UNEP)により1988年に設立された組織であり、Intergovernmental Panel on Climate Change(気候変動に関する政府間パネル)の略称である。IPCCが作成する報告書は、気候変動に関わるあらゆる場面で利用される、世界最大の科学的根拠となっている。各報告書は、複数の専門家によって作成されているが、作成前の概要決定や、作成された要旨、各種活動や予算は、加盟している各国の政府代表が出席する総会において承認されている。このことが「政府間パネル」である所以である。世界のほぼすべてである195の国と地域がIPCCに参加している。
[6] UNEPは、United Nations Environment Programmeの略称で、日本では、国際連合環境計画と呼ぶ。国際連合の機関として環境に関する諸活動の総合的な調整を行なうとともに、新たな問題に対しての国際的協力を推進することを目的としている。また、多くの国際環境条約の交渉を主催し、成立させてきた。モントリオール議定書の事務局も務めており、ワシントン条約、ボン条約、バーゼル条約、生物多様性条約などの条約の管理も行っている。
[7] 「予防原則(Precautionary Principle)」は、環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼす仮説上の恐れがある場合、科学的に因果関係が十分証明されない状況でも、規制措置を可能にする制度や考え方のこと。1990年頃から欧米を中心に取り入れられてきた概念である。「疑わしいものはすべて禁止」といった極論に理解される場合もあり、行政機関などはこの言葉の使用に慎重である。「予防措置原則」とも言う。欧州では、この概念を食品安全など人の健康全般に関する分野にも拡大適用しはじめたが、他の国・地域では必ずしも受け入れられていない。
[8] 野心的国際連携協働は、経済成長や雇用を犠牲にすることなく、全球的な循環型社会や脱炭素社会の構築に貢献するもので合理的理由があり、個々に対応するよりも、国際連携協働据える方が、早く、安く、確実に目標を達成できる。加えて、野心的な国際連携協働により、公正な競争、安心した投資ができ、予測可能で一貫した環境が構築され、、資源循環に積極的に取り組む企業活動を強力に後押しすることで、経済的繁栄を持続可能な地球環境対策が一石二鳥でシナジーを生み乍ら、人類の幸福に貢献する。
4.国際プラスチック条約(The Global Plastics Treaty) [10]の経済的合理性
野心的な国際連携協働が必要な明白な合理的理由があることを証明する画期的な報告書がある。
つい先日2025年6月25日に、国際プラスチック条約企業連合(Business Coalition for a Global Plastics Treaty)から公開された報告書「国際プラスチック条約の経済的合理性(The economic rationale for a Global Plastics Treaty underpinned by mandatory and harmonised regulation Article)」(June 5, 2025)である[11]。
この報告書は、国際プラスチック条約の意義を担保すべく、法的拘束力のある調和の取れたルールを基盤とすることが経済活動にも有益であることを示す新たな分析結果を示した。野心的な国際連携協働が必要な明白かつ合理的な理由を証明する画期的な証左である[12]。この報告書は、企業連合がSYSTEMIQ社[13]に委託し、プラスチック汚染根絶に向けた対策を各国で分散したルールとなる場合と調和の取れたルールに基づく場合との経済的合理性を比較分析した[14]。その分析の結果、法的拘束力のある調和の取れたルールに基づく条約が経済活動にも有益であることが定量的に示された。
本報告書では、下図【図1】の通り、世界中で不適切に管理されるプラスチック廃棄物は、「国際ルール」の導入により、分散ルールの場合の1億2100万トンに比べ、9300万トンと、23%も大幅に削減できることが検証されている。野心的な国際連携協働として、法的拘束力のある調和の取れたルールに基づく条約の有効性を示す証左である。

【図1】不適切に処理されるプラスチック廃棄物の量の「現状維持」「分散ルール」「国際ルール」の比較(2040年)
(出所) 三沢行弘(2025)「国際プラスチック条約企業連合野心的条約の企業への意義を考える」
(注)単位: 100万トン。青が「現状維持」、黄色が「分散ルール」、緑が「国際ルール」の場合。
また、下図【図2】は、プラスチックの水平リサイクルによる再生素材につき、製品・化学物質規制(3条)、製品設計基準(5条)、廃棄物管理・EPR(8条)に「国際ルール」を導入することで、分散ルールの場合と比べ、2040年に世界で77%、日本で90%増やすことができることを示す検証結果を示している。

【図2】プラスチックの水平リサイクルによる再生素材生産量の「現状維持」「分散ルール」「国際ルール」の比較(2040年)
(出所) 三沢行弘(2025)「国際プラスチック条約企業連合野心的条約の企業への意義を考える」
(注)単位: 100万トン。青が「現状維持」、黄色が「分散ルール」、緑が「国際ルール」の場合。
こうした分析結果は、法的拘束力のある調和の取れたルールを基盤とすることが経済活動にも有益であることを示している。
目下、各国での異なる規制がプラスチック汚染対策の進展を著しく遅らせる実態がある中、「国際プラスチック条約(The Global Plastics Treaty)」の早期実現が喫緊の課題となっている。製品設計、段階的廃止、EPR(拡大生産者責任)に関する明確な規定を持つ統一された規制は、イノベーションを大いに促進するだけでなく、企業にとって公平な競争の場を創出する大きなメリットがある。目下、国際条約交渉は、自国経済への打撃を懸念するサウジアラビアやイラン、ロシアなどの産油国が強硬に反対しており、石油から作られるプラスチックの素材(ポリマー)生産にかかわる条文の扱い等で意見対立もあり難航しているが、いまこそ、プラスチック汚染阻止と資源再活用のためのサーキュラーエコノミーへの移行に向けた野心的な条約の早期実現が求められている。
本報告書は、総括として、「国際プラスチック条約(The Global Plastics Treaty)」条約の経済合理性について、以下5点、論点整理をしている。
【「国際プラスチック条約(The Global Plastics Treaty)」条約の経済合理性】
●調和された規制は投資・雇用・廃棄物管理を効率化し、環境・社会的な利益をもたらす。
●国際協力の枠組み(例:資金メカニズム、同意システム)は、公平かつ実効的な実施を可能にする。
●汚染と製造が生む経済負担を抑え、リサイクル・循環経済への移行を促進する。
●市場の安定化には、生産の制限と需要シェーピングが必要。
●化学物質規制による健康コスト削減は、社会的正義と経済合理性の観点からも強力な論拠となる。
ちなみに、本報告書の内容詳細は、以下の通りである。
(参考)国際プラスチック条約の経済的合理性についての報告書の内容詳細
「必須かつ調和された規制を基盤とする国際プラスチック条約の経済的合理性」
(The Economic Rationale for a Global Plastics Treaty underpinned by Mandatory and Harmonised Regulation)
①経済的に調和された規制の優位性(Systemiqによる分析)
Systemiqが「Business Coalition for a Global Plastics Treaty」のために行った分析によれば、世界的に統一された強制的規制を導入することで、以下のような経済的効果が期待される。
●インフラ投資の促進:最大で 5,760億ドル のインフラ投資を誘発。
●問題のあるプラスチック廃棄の削減:除去効果が2倍になる。
●再生材使用の増加:再生プラスチック含有量が 77% 増加。
●廃棄物の適切処理率向上:管理されていないプラスチックごみが 23% 減少。
●社会的・環境的利益の創出:雇用の安定化、投資コストの低下、資本市場に対する信頼向上など。
これらの数値は、調和された条約による経済的な利点を具体的に示すものであり、政策としての説得力を高める根拠となりうる。
②モノトーンの規制を補完する過去の制度からの教訓
モントリオール議定書では、先進国から開発途上国への資金移転メカニズムを通じて、均衡ある負担と実効性を達成した好例がある。この仕組みは、グローバル・プラスチック条約における開発途上国支援にも応用可能である。バーゼル条約のプラスチック廃棄物改正では、輸出国に事前通報と輸入国の同意を義務付けた制度を導入。これにより、先進国から途上国への廃棄物移動が抑制され、同様の制度的枠組みをグローバル条約にも導入すれば、国際協力の実効性を高めることができる。
③プラスチック汚染が経済に及ぼす負担の現状
海洋へのプラスチック汚染だけで 3,300ドル~3万3,000ドル/年 の清掃費用、観光損失などを生じさせ、汚染全体では年間 1,000億ドル が費やされている。プラスチック製造によって生じる健康被害に伴う経済的負担は、2015年時点で 2,500億ドル超。その多くは石油由来原料が安価であることに起因し、再生原料やバイオ由来素材が競争上不利な状況にある。
④過剰供給下での市場安定化の必要性
IEEFA(金融分析研究機関)の報告では、プラ樹脂市場が過剰供給と低利益率に陥っており、供給を規制しない限り市場は不安定化する恐れがあると指摘されている。全球的な生産抑制を含む条約は、リサイクル促進と需要制限と組み合わせることで、市場の健全性と投資の安定化に寄与している。
⑤健康・環境に対する化学物質規制の経済的メリット
プラスチックに含まれる有害化学物質は、人体や生態系に深刻な影響を及ぼし、以下のような巨額のコストを伴う。
●米国における特定の化学物質(例:BPAなど)による健康被害の直接・間接コストは 2,500~6,750億ドル/年。
●BPA規制により、米EUで年間6万~6万6,400人の子どもの肥満発症を防止し、36~39億ドルの医療・経済効果が見込まれる(対象が玩具に限定される場合の効果は11~27%にとどまる)。
[10] 国際プラスチック条約(The Global Plastics Treaty)は、プラスチック汚染問題解決のための法的拘束力のある国際条約。2022年3月の国連環境総会において、「プラスチック汚染を終わらせる」ための政府間交渉委員会(INC)が設置され、国際的なプラスチック規制の枠組みを作ることを目指し、2022年の国連環境総会(UNEA5.2)で各国が合意した。去年2024年11月25日から12月1日まで韓国・釜山で開催された会議には、177か国から約3,800人が参加し条約全体について交渉が行われた。今年2025年年8月5日からスイス・ジュネーブで開催されていた国連府間交渉委員会では、残念ながら、今回の会合での条文案の合意を断念し先送となってしまった。
[11] The economic rationale for a Global Plastics Treaty underpinned by mandatory and harmonised regulation Article)」(June 5, 2025)https://www.businessforplasticstreaty.org/latest/the-economic-rationale-for-a-global-plastics-treaty
[12] 目下、国際プラスチック条約(The Global Plastics Treaty)国際条約交渉は難航しているが、当該報告書の価値を減ずるものではいささかもない。2022年の国連環境総会で各国は、2024年末までにプラ汚染根絶のための法的拘束力のある国際条約を作ることを決議した。しかし、2024年11~12月に韓国であった前回交渉委で各国の意見は折り合わず合意を先送り。今回の交渉委は「延長戦」との位置づけで、今月5日に再開され、14日までの予定だった会期を1日延ばして合意が模索されたがまたも結論が出なかった。とりわけ意見対立が目立ったのは、石油から作られるプラスチックの素材(ポリマー)の「生産」にかかわる条文の扱いだ。EUや漂着ごみに悩む島しょ国などは、汚染を止めるためにはポリマーの生産量を減らす必要があると訴えた。これに対し、自国経済への打撃を懸念するサウジアラビアやイラン、ロシアなどの産油国が強硬に反対。生産規制ではなく、プラごみが環境中に流出するのを防ぐ「廃棄物管理」を強化すべきだと主張した。議長が13日に各国に示した条約草案は、最大の争点だったプラ素材(ポリマー)の生産規制に関する条文を丸ごと削除するなど、生産段階の規制に強硬に反発する産油国側に譲歩した妥協色の濃い内容だった。強い規制を求める欧州連合(EU)などが主張してきた国際的なプラ素材の生産・消費量の削減目標設定は、従来の議長案の選択肢から落とされ、同じくEUなどが求めてきた使い捨てプラ製品の段階的廃止などに関する文言も削られた。これに対し、EUや島しょ国、中南米などの国々は「許容できない」とこぞって反発。多くの点で主張に沿う草案になったはずの産油国サウジアラビアの代表からも「多くのレッドライン(譲れない一線)を越えている」と反対意見が出るなど、賛同はほとんど聞かれなかった。
[13] SYSTEMIQ社は英国のコンサルティング会社。グローバルな課題解決に向け、システム全体の設計変革推進、持続可能で公正な未来実現を目指し、協働的なシステム設計者、開発者、変革者として多面的な活動をしている。https://www.systemiq.earth/
[14] SYSTEMIQ社が分析した対象は、条約の主要な条項である「3条:プラスチック製品/化学物質規制」、「5条:製品設計」と「8条:廃棄物管理/EPR(拡大生産者責任)」である。特に、交渉会合でその動向が鍵となるとされる6カ国(日本、ブラジル、中国、インド、インドネシア、南アフリカ)についての分析を深掘りした。
5.国際司法裁判所による気候変動に関する勧告的意見(Advisory Opinion)
国際司法の立場からも、気候変動問題解決の分野で、人類にとって必要不可欠な野心的な国際連携協働を明確に裏打ちする判断が出されたことは、朗報である。
先日2025年7月23日に、オランダ・ハーグにある国際司法裁判所(International Court of Justice ;以下ICJと略)が発表した「気候変動問題のゲーム・チェンジャー」とも言うべき気候変動に関する勧告的意見(Advisory Opinion)[1]である。正式名は以下である。ICJ(2025)“Obligations of States in respect of Climate Change;The Court gives its Advisory Opinion and responds to the questions posed by the General Assembly”(No. 2025/36;23 July 2025)[2]
ICJが発表した、この気候変動に関する国家の義務および義務違反の法的帰結に関する勧告的意見は、各国政府関係者、世界中の法学者、市民社会が活発に関与した2年間にわたるプロセスの集大成で、国際法上、国家には気候変動対策をとる義務があるとする極めて重要な意見表明であった[3]。
発表の場には国連総会議長や各国代表が出席し、世界各都市でライブ配信された。発表したのは、今年2025年3月にICJ所長に選出されたばかりの岩澤雄司名誉教授[4]であった。
この勧告的意見は、すべての国家の気候システム保護義務を明確にし、1.5℃がすべての国が達成すべき目標であることを明確に示し、NDC(国が決定する貢献)について国家の裁量権を否認し、国際連携協働の義務を明確にした画期的な勧告であった。
勧告的意見は、国家がGHG排出から気候システムを保護するための適切な措置を講じないことを国際法上の不法行為だと断じ、国が定めるNDC(国が決定する貢献)のレベル(野心度)について、国家が完全な裁量権を有しているわけではないとしている。まさに、国際司法の立場からも、国際連携協働の義務を明確にしたのである。
今回、国家が個々の事情で裁量権によって判断し行動するのではなく、あくまで、1.5℃目標達成という目的のもと国際慣習法や人権法に基づく「パリ協定」など野心的な国際連携協働に対して義務を負っていることを明確にした意義は大きい。
この勧告的意見には法的拘束力はないが、ICJの権威ある法的見解が示されたことで、今後、気候変動訴訟や国際交渉等に影響を及ぼすであろうと見られている。野心的な国際連携協働が必要な明白かつ合理的な理由を、国際法の観点から担保する画期的な証左であると言える。
また、企業の排出に対しても国家が責任を持ち、清潔で健康的で持続可能な環境における人権は、他の基本的人権の享受に不可欠であるとし、Justice(公正)やequity(公平・衡平)を多くの文脈で取り上げていて、通奏低音としている。そして、気候の脆弱性によって避難してきた難民は保護されなければならず、生命の危険があるような状況下で彼らを母国に送り返すことは許されない、という義務の存在についても言及している。
この勧告的意見の肝は、「国際法上、国家には、人為的な温室効果ガス排出から気候系等を保護する義務がある」という宣言にある。
実は、この「国際法上」という部分が意味するのは、気候変動枠組条約、京都議定書、パリ協定のような気候変動対処を目的とした条約だけではない。国連海洋法条約や気候以外の国際環境条約、国際人権規約、そして慣習国際法も含まれている。慣習国際法とは、条文がない不文法であり、国家の一般的な慣行が、法として受け入れられているという確信を伴って形成されるもので、すべての国を拘束する。つまり、今回の勧告的意見は、気候関連の条約の締約国であるか否かにかかわらず、すべての国家には気候系等を保護する義務があると言っているのである。
ここまでしっかり踏み込んだ勧告的意見は前代未聞である。これが「気候変動問題のゲーム・チェンジャー」であると高く評価されている由縁である。この勧告的意見は、気候正義の観点からの不正義の是正を求める長年の戦いにおける、一つの到達点であると同時に、法の支配に基づく新たな気候変動対策の時代の幕開けを意味している。
参考までに、本勧告的意見のポイントは、以下の12点に論点整理することができる。
<勧告的意見のポイント>
1. ICJ勧告的意見は裁判官全員の完全な合意のもとに作られた「気候変動問題のゲーム・チェンジャー」といえる 。
2. 大量排出国が「国家は気候変動条約で合意した任意の義務しか負わない」と主張しようとしたのに対し、ICJ勧告的意見は明確にたとえ条約や協定の締約国でなくてもすべての国家は国際慣習法(International Customary Law)上の義務として気候システムを保護する義務があるとした 。
3. ICJ勧告的意見は国際法のもと気候システム保護のための具体的な数値目標として1.5℃がすべての国が達成すべき目標であることを明確に示した 。
4. 国が定めるNDC(国が決定する貢献)のレベル(野心度)については、国家が完全な裁量権を有しているわけではなく、1.5℃目標達成という目的のもと国際慣習法や人権法に基づく(パリ協定などに対して)追加的な義務を負っていることを明確にした 。
5. 国家が温室効果ガス(GHG)排出から気候システムを保護するための適切な措置を講じないこと(化石燃料の生産、消費、化石燃料探査許可の付与または化石燃料補助金提供を含む)がその国家に帰属する国際法上の不法行為を構成する 。
6. ICJ勧告的意見は、国家責任法に基づく国際的な義務として、そうした気候変動を促すような不法行為を停止する義務があること、被害と加害の因果関係(causation)および帰属性(attribution)も科学的知見によって確立可能であるとした。また企業の排出に対しても国家が責任を持つとした 。
7. ICJ勧告的意見は、清潔で健康的で持続可能な環境における人権は、他の基本的人権の享受に不可欠であるとした 。
8. ICJ勧告的意見は、Justice(公正)やequity(公平・衡平)を多くの文脈で取り上げていて通奏低音としている。基本的に島嶼国や途上国が主張してきたCBDRを重視していてかつ世代間の公平性についても多くの箇所で言及している 。
9. ICJ勧告的意見は、気候危機という文脈において被害を受けている国々が大排出国に対して行動の停止、回復(原状回復)、損害賠償を求めることはできるとした 。
10. ICJ勧告的意見は「ノン・ルフールマン(不送還)」の義務、すなわち気候の脆弱性によって避難してきた難民は保護されなければならず生命の危険があるような状況下で彼らを母国に送り返すことは許されないという義務の存在について言及した 。
11. ICJ勧告的意見では、国家が成立した後その構成要素の一つが(水没などで)消失しても必ずしもその国家の主権が失われるわけではないとした 。
12. 昨年3月に日本政府はICJ勧告的意見の策定過程で政府意見 を提出しているが日本政府の主張はICJの勧告的意見で悉く否定されている 。
[15] ICJは、国連の主要機関の一つであり(国連憲章第7条1項)、国連加盟国は当然ICJ規程の当事国である(同第第93条1項)。また、ICJは、国連総会や安全保障理事会、専門機関等から諮問された法律問題について、勧告的意見を出すことができる(同第96条)。ICJの勧告的意見には、法的拘束力はないが、その実質的な影響力は決して小さくない。
[16] ICJ(2025)“ Obligations of States in respect of Climate Change;The Court gives its Advisory Opinion and responds to the questions posed by the General Assembly”(No. 2025/36;23 July 2025) https://www.icj-cij.org/case/187
[17] 2023年3月29日、国連総会は、国連総会決議77/276「気候変動に係る諸国の義務に関する国際司法裁判所への勧告的意見の要請」を明確な反対国がないコンセンサスで可決した。勧告的意見の要請は2023年4月12日付の国連事務総長書簡によりICJに伝達された。国連総会がICJに付託した論点は大きく分けて以下4点であった。1)どの国際法を基準とするか?2)慣習国際法上の義務(環境に対する重大な損害の防止原則と「相当の注意」義務)は国家による温室効果ガスの排出にも適用されるか?3)気候変動問題に関する国家の義務とは何か?4)義務に違反した場合の法的帰結とは何か?これに対し、ICJは、国家は、国際法上、気候系等を保護する義務があるとし、その義務は、①気候変動関連条約、②慣習国際法、③気候変動関連以外の環境条約、④国連海洋法条約、⑤国際人権法など、複数の国際法の法源から生じる、包括的かつ拘束力のあるものであるとした。また、義務に違反することは、その国家の責任を生じさせる国際違法行為を構成するとした。そして、法的帰結としては、違法な作為(対策をとること)または不作為(対策をとらないこと)の停止、再発防止の保証の提供、そして、原因となる行為と損害との間に「十分に直接的かつ確実な因果関係」が証明されれば、違法行為を行った国は、被害国に対して「完全な賠償」(full reparation)を行う義務を負うとした。
[18] ちなみにICJ所長の日本からの選出は皇后雅子さまの実父小和田恆氏(2009年~2012年)に続いて2人目となる。
6.地球規模の存亡に関わる危機の時代における「蜘蛛の糸」
ICJ勧告的意見の結論部分に、以下の節がある。
「…国連総会によって提起された問題は、単なる法的な問題を越えている。あらゆる生命体と我々の惑星の健全性そのものを危うくする、地球規模の存亡に関わる問題である。国連総会によってその権威が援用された国際法は、この問題の解決において重要ではあるが、究極的には限られた役割しか持たない。この困難かつ自ら招いた問題への完全な解決策は、法学、科学、経済学、その他を問わず、人類のあらゆる知識分野の貢献を必要とする。何よりも、永続的かつ満足のいく解決策には、我々自身と、まだ見ぬ将来世代の未来を確かなものにするために、個人、社会、政治の各レベルにおいて、我々の習慣、快適さ、そして現在の生活様式を変えるという、人類の意思と英知が必要とされる。」[19]
むろん、法とて万能ではないが、気候危機問題やプラスチック汚染問題といった全人類に関わる地球規模の喫緊の課題解決において、もはや、身勝手に、自国の都合や利害を優先し、みんなで協力して問題解決に向かおうとする国際連携協働を蹂躙することはできまい。カンダタのような生き方では、結局、畢竟、よい結果は得れないからである。
「分断の時代」と言えている現代、いまこそ、地球規模の存亡に関わる問題に直面している人類にとって、グローバルなコンセンサスとそれを実現するための野心的な国際連携の仕組みが必要である。
気候危機問題やプラスチック汚染問題といった深刻な地球環境問題に対して、「ダイナミック・ケイパビリティ」の不全の問題を解決し「全体最適」の視座をもって、環境の変化をいち早く感知し、そこに新しい機会を見出し、それを捕捉して絶えず自己変容していくことが喫緊の課題である。
本稿では、過去の先行研究成果や最近の国際法の動向等を念頭に、論点整理を試み、各国が独自で個別に取り組むより、国際連携協働の方が、最終的に、個々の国々が享受できる便益が大きいことについて再検証した。そして、国際連携協働の合理的正当性は自明であることも再確認した。
人類にとって、国際連携協働は、唯一残された「蜘蛛の糸」である。
その含意は極めて重要であると考える。
もはや、運命共同体「宇宙船地球号」に乗船している人類にとって「自分さえよければいい」といったカンダタのような考え方を受け入れる猶予はない。
なぜなら、この地球というちっぽけな青い惑星上に、もはや「対岸の火事」は、ないからである。
[19] (出所)ICJ(2025)“ Obligations of States in respect of Climate Change;The Court gives its Advisory Opinion and responds to the questions posed by the General Assembly”(No. 2025/36;23 July 2025)
(end of documents)











