
世界最大級の“電子機器の墓場”と言われる、ガーナのスラム街アグボグブロシー。その地を活動拠点として、EV事業、リサイクル事業、農業の事業活動を展開し、現地のゴミの削減や大気・土壌汚染を改善に挑みながら、新たな雇用創出に取り組む企業がある。その名はMAGO MOTORS JAPAN株式会社。現地に積み上がる先進国からの廃棄物でアートを制作する美術家でもある長坂真護氏が代表を務める同社が目指すのは、2030年までに現地雇用1万人を実現すること。クリーンな労働環境と適正な賃金を付与することで「スラム撲滅」の達成へ走りつづける事業活動について社員の岩田きよら氏にインタビューした。
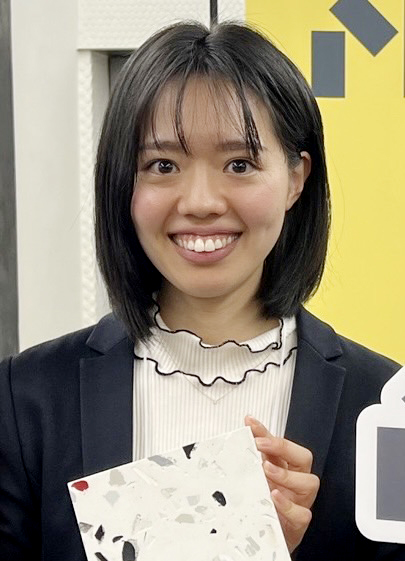
問題解決する側の人になろう
── MAGO MOTORS JAPAN株式会社に入社を決めた理由は何でしょうか。
岩田:私は、以前からサステナブルやエシカルなどに関心があり、長坂が上野の森美術館で個展を行うことを知りました。そのときに長坂がMAGO MOTORS JAPANで行っている活動も知り、本気で社会課題の解決に取り組もうとする姿勢に感動を覚えました。
私自身も課題解決する側の人間になりたいと思い、その後、社員の募集があり、ご縁をいただき参加することができました。
── 現在、この会社でどのような業務に取り組んでいますか。
岩田:当社が目標とする2030年までに1万人の雇用に向けて、メインであるアート事業をはじめ、リサイクル事業や農業事業を日本で展開するため、現地とオンライン等でやりとりしながら、様々な業務を担当しています。社員はまだわずかであるため、私自身もアートの紹介、建材の販売、モリンガティーの開発や販売など色々な経験をさせていただいております。目標である雇用1万人の達成に向けてブレない活動に、とてもやりがいを感じています。
選択肢がない中、有毒ガスの中で働く人々
── その活動拠点があり、世界最大級の“電子機器の墓場”と言われる、ガーナのスラム街アグボグブロシーはどのような課題に直面しているのでしょうか。
岩田:アグボグブロシーには、約東京ドーム30個分の分の広さを持つ電子機器の廃棄場所があります。それが世界最大級の“電子機器の墓場”と呼ばれる場所になります。そのエリア一帯は電子機器で埋め尽くされ、いろいろなところで現地の人が野焼きをする光景が見られます。燃やすことでプラスチックを溶かし、中から鉄や銅などの金属を取り出す仕事をしているのです。
貰える給料は1日5ドルほどです。しかも電子機器を燃やせば有ガスが発生します。そこで働く人々は、頭痛や吐き気などを痛み止めで抑えながら仕事をしています。では、なぜ、そのような過酷な仕事に就いているのでしょうか。それは残念ながら、日本のような職の選択肢がほとんどないからです。
また、この野焼きの仕事が現地の人に取ってはたくさん稼げる仕事の1つとなっています。当社ではそんなアグボグブロシーから、1人でも多くの人を雇えるようにリサイクル工場の設立。農業。EV事業などを行なっています。


文化を土台に経済、社会貢献の歯車を回す
── MAGO MOTORS JAPAN株式会社は、「文化」「経済」「社会貢献」の3つの歯車を持続的に回しながら、経済活動を通じて社会課題の解決を目指す「サステナブル・キャピタリズム(持続可能な資本主義)」を事業コンセプトとして活動しています。この3つの歯車とは、具体的には何に当たりますか。
岩田:文化とは、長坂の電子廃材を使った現代アート作品を販売することがベースになります。現地の廃材を使うというこの創作活動は、表現をすればするほどガーナのスラム街からゴミを減らすことができます。そして、スラム街の現状を伝えられます。また、同時に、そこには、売り上げも生まれます。その売り上げは、現地のリサイクル工場の建設に使われるなど、事業投資を行っております。
また、現地のリサイクル工場にて、電子機器を粉砕したものを、セメントと混ぜてタイルにして、販売も行なっています。建材としてもゴミを減らし、その売り上げもさらなる事業投資に使われます。「文化」を通じて、経済を動かし、さらには、「社会貢献」にもなる。3つの歯車が確かにかみ合い、回転していることを実感しています。
── 2030年までに現地雇用1万人という目標達成への進捗具合はいかかでしょうか。
岩田:現時点では、62名ほどです(2024年9月現在)。まだまだですが、これから加速に向けて全スタッフが一丸となって取り組んでいます。
2025年に開幕する大阪・関西万博では、1970年の大阪万博のシンボルであった太陽の塔と同じ敷地に長坂の作品である月の塔が展示される予定です。大きなイベントなどを通じて、長坂や当社の取り組みがより多くの人に知られ、目標達成に向けて拍車がかかることを期待しています。
── 気候変動が深刻化し、分断や憎悪が広がり、希望が持ちにくい世界。岩田さんのような若い世代はその現実にどう向き合っていけばよいとお考えでしょうか。
岩田:私は、少しでも興味あること。好きなこと。をより深く知ってほしいなと思っています。どんなことでもいいなと思います。私は、自然が好きで、もっと知りたいと思い、調べていると環境問題の現実を知りました。さらに、共感できる仲間や一緒に挑戦したり、相談できたりする友人を見つけることができ、今、毎日、楽しく過ごすことが出来ています。
── ありがとうございました。











